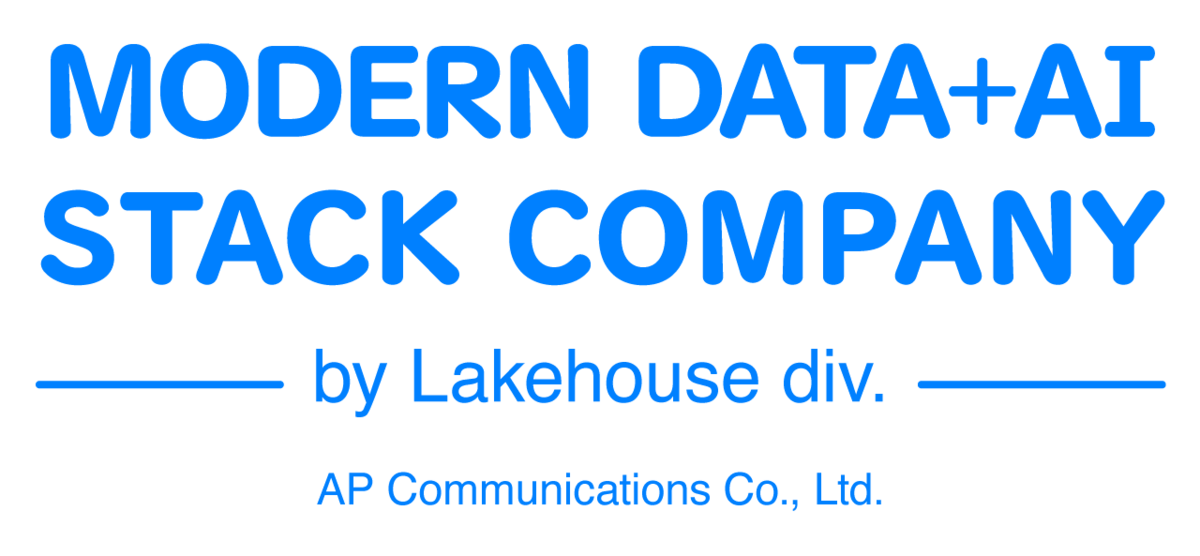Unity Catalogの活用:データとAIのガバナンスへの新たなアプローチ
GLB事業部Global Engineering部 ヨハンです。
こんにちは、皆さん。今回は、データとAIのガバナンスについての興味深い講演を取り上げます。そのタイトルは「A Technical Deep Dive into Unity Catalog's Practitioner Playbook」で、発表者はDatabricksの経験豊富な製品リーダーであるIshan Papaさんと、データテクノロジーの専門家であるIfy Derekさんです。彼らは、Unity Catalogを活用したデータとAIのガバナンスについて詳しく説明してくれました。 このブログは全3部構成の第2部となります。前回のブログでは、Unity CatalogがデータとAIのガバナンスレイヤーであり、Lakehouseプラットフォーム内での役割や、クラウドプロバイダとの関係性について解説しました。今回は、Unity Catalogのデータの登録方法やセキュリティ機能、データの検索とラインナップ機能について詳しく見ていきましょう。
メタストアとUnity Catalog
Unity Catalogでは、メタストアという概念が導入されています。これは、テーブルを格納し、管理するための管理データソースです。Unity Catalogとメタストアの関係性について理解することで、データの管理がより効率的になります。
メタストア:テーブルの格納と管理を行うデータソース
Unity Catalog:メタストアを活用し、データとAIのガバナンスを行うツール
Unityのボリュームの特性と利点
Unityのボリュームとは、非表形式のデータセット用に設計された機能です。これにより、様々な形式のデータを一元的に管理することが可能になります。Unityのボリュームの特性と利点を理解することで、データの管理がより柔軟になります。
Unityのボリューム:非表形式のデータセット用に設計された機能
特性と利点:様々な形式のデータを一元的に管理可能
データ管理システムのアクセス制御機能
Unity Catalogでは、データ管理システムのアクセス制御機能についても詳しく説明されました。これにより、データのセキュリティを確保しつつ、必要なユーザーに対して適切なアクセス権限を付与することが可能になります。
- アクセス制御機能:データのセキュリティを確保し、適切なアクセス権限を付与する機能
Unity Catalogの活用により、データとAIのガバナンスがより効率的に行えることがわかりました。これらの機能を理解し、適切に活用することで、データ管理の効率化とセキュリティの強化が可能になります。
Unity Catalogを活用したデータとAIのガバナンス
Unity Catalogは、データ管理における強力な系統、検索、監査機能を提供するツールであり、その特性と利点を理解することで、データの検索とラインナップ機能を最大限に活用することが可能となります。
CI/CDパイプラインの作成とアクセス制御
まず、Unity Catalogを使用してCI/CDパイプラインを作成する利点について説明します。CI/CDパイプラインとは、Continuous Integration(継続的インテグレーション)とContinuous Delivery(継続的デリバリー)の略で、開発からデプロイまでの一連のプロセスを自動化する手法を指します。 Unity Catalogを使用すると、以下のような利点があります。
正確なパーミッションとアクセス制御を確立できる
データの一貫性を保つことが可能
データの更新や変更をリアルタイムで反映できる
これらの機能により、データの管理が容易になり、データの信頼性も向上します。
データ管理の強化
次に、Unity Catalogのデータ管理における強力な系統、検索、監査機能について説明します。Unity Catalogを採用することで、以下のような特性と利点が得られます。
データの系統を明確に把握できる
必要なデータを素早く検索できる
データの利用状況を監査できる
これらの機能により、データの管理が一層強化され、データの利用効率も大幅に向上します。 Unity Catalogを活用すれば、データとAIのガバナンスを効率的に行うことが可能となります。データの検索とラインナップ機能を最大限に活用し、データ管理を一層強化しましょう。
データ共有の新たな可能性:デルタ共有
この講演では、Unity Catalogを活用したデータとAIのガバナンスについて詳しく説明されました。その中でも特に注目すべきは、オープンデータ共有の可能性についてです。デルタ共有という新たな概念が紹介され、Oracle、Dell、Cloudflare R2などの企業がすでにこの技術を採用していることが明らかにされました。
デルタ共有とは?
デルタ共有とは、データの共有と同期を可能にする新たな技術です。これにより、データの所有者と利用者間でデータの一貫性を保ちつつ、効率的にデータを共有することが可能になります。
デルタ共有の採用企業
この新たな技術は、すでにOracle、Dell、Cloudflare R2などの大手企業に採用されています。これらの企業は、デルタ共有を通じてデータの一貫性を保ちつつ、効率的にデータを共有し、ビジネスの効率化を図っています。
デルタ共有のメリット
デルタ共有の最大のメリットは、データの一貫性を保ちつつ、効率的にデータを共有できることです。これにより、データの所有者と利用者間でのデータの不一致や誤解を防ぎ、データの信頼性を高めることができます。 また、デルタ共有は、データの所有者がデータの利用者に対して、どのデータをどの程度共有するかを細かく制御できるため、データのセキュリティも確保できます。
まとめ
Unity Catalogを活用したデータとAIのガバナンスについての講演では、デルタ共有という新たなデータ共有の概念が紹介されました。この技術は、データの一貫性を保ちつつ、効率的にデータを共有することを可能にし、すでに多くの企業に採用されています。データの共有と同期の新たな可能性を秘めたデルタ共有に、今後も注目が集まりそうです。 次回のブログでは、Unity CatalogへのアップグレードプロセスとHiveなど他のシステムからの移行方法について詳しく見ていきます。お楽しみに!
おわりに
現地でのDAISに参加しているメンバーからの報告をもとに、セッションの内容を解説しました。 DAIS期間中では、セッションに関する記事を以下の特設サイトに順次上げていきますので、見ていただけると幸いです。
引き続きどうぞよろしくお願いします!