
- Backstageがまったく分からない人向けに概要を解説
- 非エンジニア向けになるべく分かりやすい言葉でBackstageを伝える
- Backstageの各機能がどんなものかイメージを伝える(技術的な詳細は割愛。詳細は他記事へのリンクあり)
- Backstageのビジネス的価値をマーケティング職の私が考えてまとめる
はじめに
こんにちは、ACS事業部の大澤(非エンジニア)です。 先月(2025年7月を指す)にエーピーコミュニケーションズに入社しました。 今後はBackstageをベースとした自社プロダクト「PlaTT(プラット)」を推進することをミッションとして動いていきます!
正直なところ、入社前の面接で「Backstage」という言葉を聞いたときは「ライブハウスの裏側かなにかか?」とよくわかっていませんでした...。 しかし、事業部内で話を聞くうちに、このBackstageがあらゆる開発組織の生産性向上や標準化に大きく貢献し、結果として開発に変革を起こす重要な存在だと確信しました。

具体的に何ができるのか、なぜ今これほど注目されているのか、そして私たちのビジネスにどんな価値をもたらすのか...。 非エンジニアである私が、経営陣や他部署にその重要性を説明するには、技術的な側面だけでなく、ビジネス的メリットをしっかり理解する必要があると感じています。
そこで今回のブログは、自分や私と同じような方、例えば、
「開発チームからBackstageを使いたいと言われたが、正直よくわからない」
「開発チームがBackstageの話をしているが、会話で置いてけぼりになりたくない」
「技術投資としてのBackstageのビジネス的価値を知りたい」
と思っている非エンジニアサイド(例えば、事業責任者・広報・PdMなど)に向けて書きます。 専門用語はできるだけわかりやすい言葉に変換し、Backstageの概要からそのビジネス的価値、そして導入にあたっての考慮するポイントをまとめていきます。
そもそもBackstageとは
まずは公式ページの記載を見てみましょう。
"Backstageは、開発者ポータルを構築するためのオープンソースフレームワークです。
引用元:What is Backstage? | Backstage Software Catalog and Developer Platform
一元化されたソフトウェアカタログを基盤とするBackstageは、マイクロサービスとインフラストラクチャの秩序を回復し、製品チームが自律性を損なうことなく、高品質なコードを迅速にリリースできるようにします。"
これを嚙み砕いて説明すると、開発者ポータルというのは、社内に散らばっている開発ツール、サービス、ドキュメントといったあらゆる情報を一か所に集約し、開発者が必要な情報へすぐにアクセスできるようにする「社内ポータルサイト」というイメージです。 また、オープンソースとは、ソフトウェアのソースコードが公開され、誰でも自由に利用、改変、再配布できることを指します。
そして、【マイクロサービスとインフラストラクチャの秩序を回復】【製品チームが自律性を損なうことなく、高品質なコードを迅速にリリース】の部分も噛み砕くと、
要は、細かなツールやサービスとか、プロダクトを動かすための基盤とかが社内でごちゃごちゃしているのをまとめられますよー。ただ、細かく統制しすぎて、開発スピードが落ちることもないですよー。という感じでしょうか。
なお、Backstageは音楽ストリーミングサービスのSpotifyによって開発されました。Spotifyは何百もの小さなサービスと何千人ものエンジニアを抱える大企業へと成長するにつれて、システムは複雑化し、使用するツールも増え続け、その結果、開発生産性が低下していたようで、そんな状況を打開するべくBackstageが開発されたとのことです。
公式のストーリーがあるので、翻訳して読んでみてください。
開発者ポータルは道具箱みたいな存在
この開発者ポータルを例えるなら、いわゆる開発者のための「道具箱」だと、私は考えています。

会社の中にある様々な開発ツール、サービス、説明書などを一か所にまとめて、開発者が一つの画面から、新しいソフトを作ったり、管理したり、探したりできるようになるというわけです。開発者の「考える負担」を減らし、生産的に働けるようにすることを狙いとしています。
今の時代、新しいサービスやアプリを開発するのは、まるでたくさんの道具が散らばった工場で作業をするようなものではないでしょうか。例えば、こんな感じ。(以下画像)

イメージとしては、こんな感じです。なにかと準備に時間がかかります。「いやいや、ソフトの開発は、PCあればできるし、体を動かさないじゃん!」と思うかもしれませんが、画面上でいろんなページに行ったり来たりするので頭がこんがらがるわけです。
実は、この「頭がこんがらがる」現象、つまり作業の切り替えによって集中力が途切れ、思考に負荷がかかることには「コンテキストスイッチ」という名前がついています。これこそが、開発の生産性を大きく下げる見えないコストの正体です。
広大なネットの工場に、使う道具(システムやツール)が散らばりすぎて、どこに何があるか、どう使えばいいか分からなくなり、開発者の皆さんは「本来の仕事」に集中しづらくなっています。
このような「システムがバラバラ」「情報がどこにあるか分からない」「誰が担当か不明」といった本質的でない悩みを排除して、開発者がもっと気持ちよく・効率的に働けるようにすることを目的としたのが開発者ポータルであり、それを作るためにオープンソースとして登場したのがBackstageです。
なぜ注目されているのか、について考えてみる
よく言われている理由として、DevOpsやクラウドネイティブといった開発手法(説明は割愛)の普及がよく挙げられます。しかし本記事では、あえて技術的な解説からは一歩引いて、「なぜ、それがビジネスにとって重要なのか」という大枠の視点で考えてみたいと思います。
前提として、現代ビジネスでは新規事業の迅速な立ち上げやイノベーションが重視されており、既存事業のみで生業を立てていた老舗企業も積極的に新規事業を立ち上げています。 これら新規事業について、もはやIT技術は必要不可欠だと言えるでしょう。チームは、求められる開発スピードに応えるため、常に最適なツールを探しています。
しかし、今では世界中で新しい開発ツールが次々と登場しており(まさにツールの勃興期です)、開発者は無数の選択肢の中から「自分たちのプロジェクトに本当に合うものはどれか?」を調査し、選ぶだけでも一苦労です。 こうした状況で、スピードを優先するあまり各チームがそれぞれ異なるツールを導入した結果、社内には様々なツールが乱立して情報が分散し、かえって生産性を下げるという新たな課題が生じてしまうのです 。

現代のビジネスは変化のスピードが速く、事業の方向性を転換する「ピボット」が頻繁に起こり、開発サイクルも非常に短くなっています。このような状況下では、過去に開発した資産(アセット)を有効活用することの重要性が増しています。 また、人材の流動性が高まっていることへの対応も欠かせません。これは社内の異動だけでなく、活発な転職市場を背景にした主要メンバーの退職や新たなメンバーの参加も含まれます。
情報が分散したままだと、過去の貴重な資産がどこにあるか分からず再利用できなかったり、新しく加わったメンバーが状況を把握するのに時間がかかってしまったりと、ビジネスのスピードを鈍化させる原因となります。これが、いわゆる「属人化」の問題です。
こうした開発現場の複合的な課題を解決するため、近年、企業内で利用する開発ツールや情報を一元管理し、開発者がセルフサービスで利用できる『開発者ポータル』という仕組みに注目が集まっています。これは、開発者にとっての「仕事の入り口」となる場所であり、必要なツールや情報に迷わずアクセスできる「コックピット」のようなものと言えます。

こうした背景から、開発者が「探す」時間や「悩む」時間を減らし、本来の開発業務に集中できる環境を整えることが、企業の競争力に直結するため、Backstageのような開発者ポータルが今、注目を集めていると考えています。
Backstageの主要な機能を確認してみる
Backstageには開発者の体験を向上させるための機能がたくさん備わっています。 ここでは、その中でも特に中心的とされる以下3つの機能を見ていきましょう。
- 「カタログ機能」
- 「テンプレート機能」
- 「ドキュメント管理」
なお、各機能の技術的な詳細については、当社のスペシャリストがまとめた解説記事があります。そのため今回は、非エンジニアの視点から「それを使うと、どんないいことがあるのか?」というイメージを掴むことに焦点をあてていきます。
カタログ機能(Software Catalog)
ソフトウェアカタログは、社内に存在する全てのソフトウェア資産を網羅した、いわば「社内システム版のWikipedia」です。このカタログを見れば、各ソフトウェアが「どのようなもので」「誰が責任者(オーナー)で」「他のどのシステムと繋がっているのか」といった情報が一目で分かります。
このように、社内のあらゆるソフトウェア情報が一元化されていることで、何かあった時に誰に聞けばよいかすぐに分かり、同じようなシステムを重複して開発してしまうといった無駄も防げるようになります。 こうした機能が、後のセクションで記述する生産性向上や経営判断の迅速化といったビジネス価値の土台となると考えています!
※機能の詳細な説明については、以下の記事でご覧いただけます。 techblog.ap-com.co.jp
テンプレート機能(Software Template)
先ほどのソフトウェアカタログが「社内に存在するものを知る・探す」ための機能だったのに対し、このテンプレート機能は「新しくものを作る」ための機能です。 この二つの違いを理解するために、カタログが「完成した家の設計図を集めたライブラリ」だとすれば、テンプレートは「承認済みのパーツが揃った家の建築キット」だとイメージしてください。
この「建築キット」には、会社が定めたセキュリティ基準や、開発に必要なツールの連携、基本的な設定など、新しい家(サービス)を建てる上で不可欠な土台や骨組みが全て含まれています。開発者は、このキットを選ぶだけで、これまで時間のかかっていた面倒な初期設定を数クリックで完了させ、すぐに新しいサービスの中身を作るという、本来の創造的な作業に取り掛かることができるのです。
これにより、開発の立ち上げにかかる時間が大幅に短縮されるだけでなく、全ての新しいプロジェクトが、会社の定める品質やセキュリティ基準を最初から満たした状態でスタートできるようになります。
※機能の詳細な説明については、以下の記事でご覧いただけます。 techblog.ap-com.co.jp
ドキュメント管理(TechDocs)
多くの会社で課題となりがちなのが、システムに関する説明書やマニュアルの管理です。情報が古かったり、保管場所がバラバラで、必要な情報を見つけるだけで時間がかかってしまうことは珍しくありません。Backstageのドキュメント管理機能「TechDocs」は、この問題を解決するための仕組みです。
TechDocsの最大の特徴は、ソフトウェア本体(コード)と、その「取扱説明書」(ドキュメント)を、常に同じ場所でセットで管理するという考え方です。開発者がソフトウェアを更新する際には、関連する説明書も一緒に更新することが促されるため、「説明書だけ情報が古い」という事態を防ぎます。
こうして管理されたドキュメントは全てBackstage上で統一された見やすいフォーマットで表示されます。これにより、開発者に限らず誰でも必要な情報をすぐに見つけ出すことができ、特定の人しか仕様を知らないといった「属人化」を解消します。この知識共有の円滑化が、後のセクションで解説する組織全体の生産性向上という価値の源泉となります。
※機能の詳細な説明については、以下の記事でご覧いただけます。 techblog.ap-com.co.jp
非エンジニア目線でビジネス的価値を考える

Time-to-Marketの短縮とROIの最大化
「探す時間」を「価値を創る時間」に変えること。これがBackstageがもたらす生産性向上の本質です。開発者が本当に集中すべきなのは、ビジネス課題を解決するための設計や、新しいアイデアを形にするといった創造的な活動ですが、実際には「あのドキュメントはどこだっけ」「この機能の担当者は誰だ?」といった情報探しや、開発環境の準備といった付随的な作業に多くの時間が奪われています。
Backstageは、この「本来の業務ではない時間」を徹底的に削減することで、「圧倒的な開発スピードの実現」を可能にします。例えば、テンプレート機能を使えば数クリックで開発を始められ、カタログ機能で既存の資産を再利用すれば、ゼロから作る手間を省けます。
こうした一つ一つの時間短縮が、新しい製品やサービスを企画してから市場に投入するまでの時間、いわゆる「TTM(Time-to-Market/タイム・トゥ・マーケット)」を大幅に短縮する原動力となります。これが競合優位性にも繋がり、開発投資のROI(投資対効果)を最大化に貢献できると考えています。
属人化の解消とナレッジマネジメントの最適化
「あの件、誰に聞けばいいんだっけ…?」会議やチャットで、そんなやり取りに時間を費やした経験はありませんか。Backstageは、そのような質問を古い慣習にする力をもっています。Backstageがもたらすのは「組織のサイロを破壊する連携力」です。サイロ化とは、組織やシステム、データなどが互いに連携せず、孤立・分断されている状態のことですね。
ソフトウェアカタログを見れば、誰がどのシステムの責任者か一目瞭然。また、TechDocsによって、これまで個人のPCや頭の中にしかなかった情報が「常に最新の取扱説明書」として一元管理されます。
これにより、担当者が不在でも、あるいは退職してしまっても、組織から知識という貴重な資産が失われることを防ぎます。新しく加わったメンバーも、必要な情報を自ら見つけ出すことができるため、チーム全体のコミュニケーションコストが劇的に下がり、組織全体の力が底上げされるわけです。
全社的な品質保証(QA)とセキュリティレベルの向上
ビジネスの成長には攻めの姿勢が不可欠ですが、それを支える「守りのDX」もまた重要です。Backstageは、開発の標準化を通じて、企業の信頼を支える守りの基盤を構築します。
Backstageが目指すのは「揺るぎない品質と信頼性の確保」です。テンプレート機能を使えば、セキュリティやコンプライアンスの基準をクリアした「お墨付き」の環境で、全ての開発をスタートできます。開発者個人のスキルや経験に依存することなく、会社として守るべきルールを仕組みとして組み込むことで、品質のバラつきをなくし、手戻りやミスのリスクを大幅に低減します。
これは、お客様に安定したサービスを届け続けるという信頼性の向上はもちろん、万が一のセキュリティインシデントを防ぐという経営上のリスク管理にも直結します。統一されたルールの上でこそ、開発者は安心して新しい挑戦に集中できるのです。
データドリブンな技術投資判断とアセットマネジメント
Backstageは守りだけでなく、「攻めのDX」を加速させる武器にもなります。その鍵は、これまで見えなかった自社の技術資産を「見える化」することにあります。 ソフトウェアカタログは、単なる開発者向けの道具ではありません。経営者や事業責任者にとっては、会社の「未来を創るための羅針盤」となり得ます。
カタログを分析すれば、「どの領域に開発リソースが集中しているか」「どのシステムが古くなっていて、刷新が必要か(技術的負債)」「どの資産を組み合わせれば新しい価値を生み出せるか」といった、データに基づいた客観的な議論が可能になります。
これまでは現場の感覚に頼りがちだった技術戦略や投資判断を、具体的なデータに基づいて行えるようになる。これは、限りある経営資源を最も効果的な場所に投下し、持続的なイノベーションを生み出すための、強力な経営基盤となるでしょう。
導入する際の現実や課題
 ここまでBackstageの様々なメリットをお伝えしてきましたが、最後に、導入を検討する上で知っておくべき現実的な側面と課題にも触れておきます。
Backstageは魔法の杖ではなく、その価値を最大限に引き出すためにはいくつかの理解が必要です。
ここまでBackstageの様々なメリットをお伝えしてきましたが、最後に、導入を検討する上で知っておくべき現実的な側面と課題にも触れておきます。
Backstageは魔法の杖ではなく、その価値を最大限に引き出すためにはいくつかの理解が必要です。
「完成品」ではなく「骨組み」という現実
Backstageの価値を理解する上で最も重要なのは、これが「完成品のソフトウェア」というよりは、非常に優れた「骨組み(フレームワーク)」であるという点です。導入してすぐに全ての機能が使えるわけではなく、自社の開発文化や使用ツールに合わせて「育てていく」必要があります。
具体的には、社内で使っているコミュニケーションツールや、開発したソフトウェアのテストから公開までを自動化してくれる仕組み(CI/CDツール)と連携させるためのプラグインの選定・設定、自社独自の開発ルールを盛り込んだテンプレートの作成といった作業が不可欠です。まさに、開発者を「社内の顧客」ととらえ、彼らの意見を聞きながら継続的に改善していく「プロダクト開発」に近い活動と言えるでしょう。
長期的な価値を生むための「投資」
前述の通り、Backstageは自社で育てていく必要があるため、その導入と運用には相応の時間とリソースの「投資」が必要になります。特に、この取り組みを専門で担当するチームを配置することが成功の鍵となります。
このチームが開発者全体の生産性を引き上げるための基盤を整備することで、個々の開発チームは製品開発という本来のミッションに、より集中できるようになります。これは、目先のコストではなく、将来にわたって組織全体の生産性を底上げし続けるための、極めてROIの高い戦略的投資だと考えるのがよいでしょう。
商用サービスというもう一つの選択肢
もし、社内に専門チームを立ち上げるリソースがない、あるいは、より早くBackstageの価値を享受したいと考える場合、専門企業が提供する運用代行サービスや、導入支援サービスは選択肢となります。
自社でBackstageを構築・運用するアプローチは、いわば「持ち家」を建てるようなものです。自由に設計できる一方、土地探しから設計、建設、メンテナンスまで全て自分たちで行う必要があります。もし、この手間やコストをかけずに、すぐにでもBackstageの価値を享受したいと考えるならば、「賃貸」や「分譲マンション」にあたる商用サービスが有力な選択肢となります。
もちろん、自社で構築するほどの自由度はないかもしれませんが、「餅は餅屋」に任せることで、本来注力すべきビジネス開発にリソースを集中させることができます。自社の規模や技術力、事業の優先順位を考慮し、「自社で育てる」か「サービスを利用するか」を判断することが重要です。
おわりに
本記事では、非エンジニアの視点からBackstageの概要からビジネスにもたらす価値、そして導入する上での課題までを考えてみました。
現代のソフトウェア開発が抱える「複雑さ」という課題に対し、Backstageは開発に必要なツールや情報を一元化し、開発者が本来の創造的な仕事に集中できる環境を整えます。それは、単なる開発効率化ツールに留まりません。開発スピードの向上、属人化の解消による組織力の強化、全社的な品質・セキュリティの向上、そしてデータに基づいた経営判断の実現——。これら全てが、企業の競争力に直結する、極めて重要な経営課題の解決策となるのです。
もちろん、その価値を最大限に引き出すには、導入して終わりではなく、社内の開発者を「顧客」ととらえ、継続的に改善していく「プロダクト」としての視点が不可欠です。
最後に、この開発の「舞台裏」を整えることの重要性について、少しだけ私の個人的な話をさせてください。
余談ですが、私は過去に映像制作(CMや番組)の現場にいたことがあります。舞台の上では演者さんが輝いていますが、その裏側では音響、照明、大道具、小道具といった多くのスタッフが活躍しています。また印象的だったのは舞台袖の道具置き場が驚くほど整理整頓されていることでした。次に使う道具がすぐに取り出せる、誰が何を担当しているか明確になっている。このスポットライトの当たらない「舞台裏」の効率性こそが、実は表舞台のパフォーマンスの質を決定づけているのです。
開発者ポータルがやろうとしていることも、これと全く同じだと思っています。皆さんの会社のビジネスという最高のパフォーマンスを支えるために、その「舞台裏」である開発現場を、最高の状態に整えてみてはいかがでしょうか。
本ブログは以上になります。ここまでお読みいただきありがとうございました。
私の所属するACS事業部では、開発者ポータルBackstage、Azure AI Serviceなどを活用し、Platform Engineering+AIの推進・内製化のご支援をしております。
www.ap-com.co.jp www.ap-com.co.jp www.ap-com.co.jp
また、一緒に働いていただける仲間も募集中です!
我々の事業部のCultureDeckはこちらです。
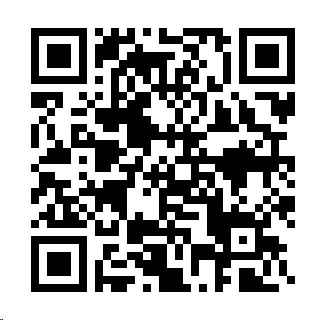 www.ap-com.co.jp
今年もまだまだ組織規模拡大中なので、ご興味を持っていただけましたらぜひお声がけください。
www.ap-com.co.jp
www.ap-com.co.jp
今年もまだまだ組織規模拡大中なので、ご興味を持っていただけましたらぜひお声がけください。
www.ap-com.co.jp